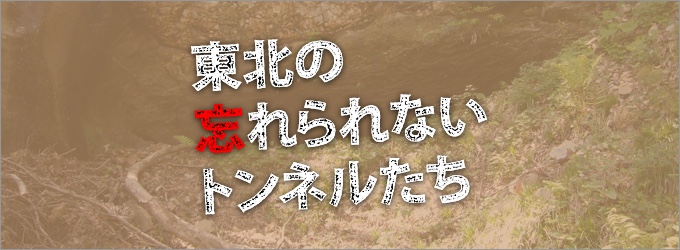本記事では、東北各地で今もなお活躍し、或いは役目を終えて静かに眠る、そんな歴史深い隧道(=トンネル)たちを道路愛好家の目線で紹介する。土木技術が今日より遙かに貧弱だった時代から、交通という文明の根本を文字通り日陰に立って支え続けた偉大な功労者の活躍を伝えたい。
会津っぽの反骨精神が生んだ手掘りの隧道
会津若松と新発田(新潟県)を結んだ近世の越後街道は、会津盆地を西に出ると間もなく束松峠を越えていた。現在も、自動車では通れない峠道に、一里塚や茶屋の跡が残っており、峠の眺めの良さと相まって、歴史好きのハイカーに人気のスポットとなっている。かつては多くの旅人で賑わい、今は静かな余生を送るこの古い峠に、明治の会津っぽたちの反骨精神を象徴するような手掘りの隧道が現存している。その名を束松洞門という。

 洞門東坑口の威容。長年の風化と崩れた土砂の堆積により、見上げるような位置に口を開けている。しかも巨大だ。
洞門東坑口の威容。長年の風化と崩れた土砂の堆積により、見上げるような位置に口を開けている。しかも巨大だ。
 宿場の雰囲気を色濃く残す麓の天屋・本名(ほんな)集落。中央の道を境に右が天屋、左が本名である。近世まで越後街道の間(あいの)宿だった
宿場の雰囲気を色濃く残す麓の天屋・本名(ほんな)集落。中央の道を境に右が天屋、左が本名である。近世まで越後街道の間(あいの)宿だった 集落の外れから峠への山道が始まる。いきなり左右に分岐しているが、ここから旧街道(左)と明治新道が絡み合うようにそれぞれの頂上を目指している
集落の外れから峠への山道が始まる。いきなり左右に分岐しているが、ここから旧街道(左)と明治新道が絡み合うようにそれぞれの頂上を目指している長年の風化を受けて、天の岩戸を思わせる威容に変じた坑口は、人と道との深い関わりを刻む無言のモニュメントとして、見る者に訴えかける迫力がある。
峠に洞門を掘ったのは、旅人の姿とともに遠くへ行ってしまった繁栄を、もう一度取り戻したいと願った旧街道筋の人々だった。明治15年に福島県令となった三島通庸(みちつね)は、強権をもって「会津三方(さんぽう)道路」(※)の建設を推し進めたが、このときに越後街道(当時の正式名は「仮定県道一等越後街道」)を束松峠から、少し遠回りだが標高の低い藤峠へ移したのである。
※会津若松から北、西、南の三方への、隣県まで通じる総延長200キロの馬車道。越後街道もこれに組み込まれた。

 峠名の由来となった「束松」は、アカマツの地域変異種といわれ、箒を逆さにしたような樹形を特徴とし、県の天然記念物にもなっている。この「三本松」もその生き残りだ
峠名の由来となった「束松」は、アカマツの地域変異種といわれ、箒を逆さにしたような樹形を特徴とし、県の天然記念物にもなっている。この「三本松」もその生き残りだ 峠の中腹、三本松付近から振り返る麓の天屋・本名集落。奥に見えるのは会津盆地の向こうにそびえる磐梯山だ
峠の中腹、三本松付近から振り返る麓の天屋・本名集落。奥に見えるのは会津盆地の向こうにそびえる磐梯山だ駆け抜ける自動車ばかりが溢れている現代とは異なり、生身の人馬が行き交う当時の道は、沿道の人々に確実な仕事と収入をもたらす存在だった。まして、二世紀以上も越後街道として繁栄を謳歌していた束松峠の沿線には、道と深く関わる生業を持つ人々が多く集まっており、片門(かたかど)や舟渡(ふなと)などのような宿場町を形成していた。ゆえに、突然の環境の変化に対応できる者はわずかであった。
だが、死活問題に直面した旧街道筋の高寺・片門・束松三カ村の人々は、この“お上”によってもたらされた逆境に、頭を垂れたままでは終わらなかった。彼らは束松峠の「県道復帰」を粘り強く陳情する傍らで、峠の直下に全長約130間(約234メートル)の洞門を掘り抜き、前後に約5キロの馬車道を開削する大工事を独自に進めたのである。この新道は片門村の元肝煎・渡辺新八郎の発案によるもので、藤峠開通の翌年にあたる明治17年には早くも着工している。まさに電光石火だ。以後は農閑期を中心に多くの村民が手弁当で工事に参加し、10年後の明治27年に見事、初志を貫徹した。


 峠道の途中にある旧街道(右)と明治新道の交差点。旧街道を行くと一里塚に出合える。両者はこの後で、また合流する
峠道の途中にある旧街道(右)と明治新道の交差点。旧街道を行くと一里塚に出合える。両者はこの後で、また合流する 明治新道を行くと、一里塚の代わりにこんな可愛らしいアイテムが発見できる。れっきとした県道であることの証し、福島県が設置した距離標(キロポスト)だ
明治新道を行くと、一里塚の代わりにこんな可愛らしいアイテムが発見できる。れっきとした県道であることの証し、福島県が設置した距離標(キロポスト)だ 旧街道(左)と明治新道の峠前最後の交差点。木の道標に従って右の道を進むと、500メートルほどで束松洞門に着く
旧街道(左)と明治新道の峠前最後の交差点。木の道標に従って右の道を進むと、500メートルほどで束松洞門に着く老朽化のため崩壊が進む洞内に、村民たちによる熾烈な工事ぶりを伝える異様な光景が残っている。両坑口を直線で結ぶ本来の坑道から、斜めに分岐する短い行き止まりの坑道の跡だ。東西の坑口付近に各1本、計2本が存在する。おそらく、これらは測量技術の未熟さに起因する、痛恨の誤掘削の痕と思われる。

 洞門東坑口の威容。長年の風化と、崩れた土砂の堆積により、見上げるような位置に口を開けている。しかも巨大だ
洞門東坑口の威容。長年の風化と、崩れた土砂の堆積により、見上げるような位置に口を開けている。しかも巨大だ 東坑口から洞内を覗くと、出口の見えない坑道が奥へと続いている。木製の支保工が崩れず残っているのには驚く
東坑口から洞内を覗くと、出口の見えない坑道が奥へと続いている。木製の支保工が崩れず残っているのには驚く 東坑口から30メートルほどの地点にある奇妙な光景。本坑の左上に行き止まりの坑道が見える。測量ミスのために誤って掘り進められた部分ではないだろうか。西坑口付近にも同様の行き止まりがある
東坑口から30メートルほどの地点にある奇妙な光景。本坑の左上に行き止まりの坑道が見える。測量ミスのために誤って掘り進められた部分ではないだろうか。西坑口付近にも同様の行き止まりがある一時的に繁栄は戻るも、落盤により終焉を迎える
こうして完成した束松新道は、藤峠経由の県道よりも少しだけ距離が短いこともあって、一定の利用者を取り戻すことに成功したようだ。日露戦争時には行軍路として使われた記録も残っている。だが大正3年に並行する鉄道(岩越線、現在のJR磐越西線)が開通した後は、街道全体の交通量は大きく減少した。
明治以来陳情を続けていた県道への復帰は、昭和9年にようやく実現するのだが、このときに県道へ昇格したのは峠の東麓の天屋集落より下側の道で、峠区間は除外された。さらに、地元の方の証言によると、ちょうどこの頃に洞門内で大きな落盤があって、また昔の峠道を使うようになっていたそうだ。戦後間もない頃に、松明を持って洞門を通り抜けたという人の話も伺ったが、既に内部は荒れ果てていて、コウモリの巣だったという。


 道路台帳によると、洞門の長さは216メートル、幅4メートル、高さ1.8メートル。随所に落盤があるが、綺麗な場所はこのような長方形の断面をしている。また、膨大な数のコウモリが生息している
道路台帳によると、洞門の長さは216メートル、幅4メートル、高さ1.8メートル。随所に落盤があるが、綺麗な場所はこのような長方形の断面をしている。また、膨大な数のコウモリが生息している 西坑口はほとんど埋没していて、アリジゴク状の穴が辛うじて貫通している。生き埋めの危険があるので、通過は自重した方がいいだろう
西坑口はほとんど埋没していて、アリジゴク状の穴が辛うじて貫通している。生き埋めの危険があるので、通過は自重した方がいいだろう 西坑口前には、一見して道はなさそうだ。よく調べると森に還った廃道が見つかるが、そこを通過するのはなかなかに大変だ
西坑口前には、一見して道はなさそうだ。よく調べると森に還った廃道が見つかるが、そこを通過するのはなかなかに大変だ 軽沢地区の景色。洞門は写真中央右側の沢を詰めた所にあるが、見ての通り、道は残っていない
軽沢地区の景色。洞門は写真中央右側の沢を詰めた所にあるが、見ての通り、道は残っていない昭和35年には、峠を境に旧束松村の領域が二分された。峠の西麓の軽沢地区は西会津町に編入され、残りは会津坂下町に入ったのである。軽沢の子どもたちが、峠を越えて片門の小学校へ通学する苦労はなくなったが、峠はさらに寂しくなった。
昭和62年にようやく峠区間が県道に編入され、同時期に峠の両側から自動車の通れる道路の建設が始まったが、途中で中断されたまま現在に至っている。なお、行政による道路管理の基礎資料である「道路台帳」では、県道は旧街道ではなく束松新道(すなわち洞門)に沿って、認定されている。
現在、洞門東側の道は、地元の人たちが刈り払いなどの手入れをしており、麓の天屋集落から徒歩1時間ほどで洞門まで楽に辿り着ける。だが西側の道は完全な廃道状態なので、辿り着くには、それなりの準備と経験が必要だ。
交通の近代化という時代の大きな流れの中で、人々が行政サービスと引き換えに取り上げられたある種の自由――自らの暮らしを守る道路を自ら計画し自ら造るという、効率的ではないが当然にあるべき欲求――を貫いた、不撓不屈の精神をもった人々がここにはいた。その証明が、束松洞門である。私はこれを愛している。

 明治16年来の越後街道である藤峠。現在は国道49号が藤トンネルで抜けており、明治の峠道は旧道になっている
明治16年来の越後街道である藤峠。現在は国道49号が藤トンネルで抜けており、明治の峠道は旧道になっている