このレポートは、「日本の廃道」2008年12月号に掲載した「特濃!廃道あるき vol.18」をリライトしたものです。
当記事は廃線探索をテーマにしており、不用意に真似をした場合、あなたの生命に危険が及ぶ可能性があります。当記事を参考にあなたが廃道へ赴き、いかなる損害を受けた場合も、作者(マイみちスト)およびみちこ編集室・道の駅連絡会は責を負いません。
所在地 秋田県男鹿市
探索日 平成20(2008)年12月3日

高さ20mの竪穴。
本来の断面のサイズが高さ3m幅2.5mほどであるのに、それが自然に崩壊するのに任せた結果、地中に高さ20mもあろうかという竪穴が出現した。そんなことがあり得るのかと訝しく思う方も多いだろうが、現実に起きていた。
もっとも、この竪穴は垂直の竪穴ではなく、斜めである。とはいえ本来の隧道の勾配としては絶対にあり得ない急傾斜である。今まで数多くの崩壊、閉塞の現場を目にしてきたが、これほどまでに高い空洞を生じたケースは初めてだった。
天井や左右の壁が茶褐色のツルンとした一枚の壁であるのに対し、足元の斜面は全て乱雑な瓦礫の山である。まさに瓦礫の山というべきものが、おおよそ45度の角度で上方へ続いている。ほとんど乾いた瓦礫の山であるから、力任せに登ろうとしても、ガラガラとやかましく崩れていき、心をざわつかせた。

瓦礫の斜面と天井は、その凹凸が対になっている。言うまでもなく、天井から剥がれ落ちた岩石がバラバラになって堆積したのが、斜面の正体である。そして、天井と斜面の隙間、つまり空洞となっている部分の高さだが、人が通るには余裕がない。低い所だと50cm程度しかないのである。
斜面を登るときの私は、自然と天井を背負う姿勢になった。崩れやすい急斜面を登るのには四つ足にならざるを得ない。膝と肘を地面につけて這い登る。この姿勢を想像して欲しいのだが、登っていく最中、低い天井に何度か背中を押され、斜面の瓦礫に鼻先を擦りつけそうになった。濃厚な土の臭いが鼻腔いっぱいに満たされる。思わぬ不快さにバランスを崩した私は足をすべらせ、転倒しかける。瓦礫でヘルメットが叩かれる。ああ、息苦しい。
そして、暑い。
熱いのではなく、暑かった。なぜか、ここは蒸し暑いのだ。風の流れのない地中世界に季節などというものはない。半年も前の夏の蒸し暑さが、通気の悪さのために保存されているような不快さがあった。真剣に汗を垂らしながら、闇の洞内を、登山した。

だいぶ登ったつもりだったが、見上げれば、まだ上がある。すさまじい大崩壊を目の当たりにして、ここまで50m近く隧道が残っていた事がすでに奇跡と思えてくる。
現地では気づかなかったのだが、写真を見ると天井にはコウモリたちが写っている。しかし数は多くない。昔はおびただしい数がいたと古老はいうが、どこへ行ったのだろう。おそらく、隧道の崩壊は彼らが長く暮らした大切なコロニーをも壊滅させたのであろう。
11:44
てっぺん

登って、登って、登ってたどり着いた場所は、幸いにして天国ではなかったが、当然、密かに望んでいた地上でもなかった。20mも登ったはずなのに、相変わらずそこは地の底だった。むしろ、これまでで一番闇の深い場所だった。万が一ここで全ての照明機材をロストしたら、発狂する自信があった。
登り着いた場所には、久々の平坦な地面があった。そして天井も立って歩けるくらいの高さがあった。まるで人の作った空間のように錯覚するが、この周囲に人の関わったものは全くない。それどころか、この空洞を目撃した人類は私が最初であろうとも思う。破滅的な隧道の崩壊、それに伴う空洞の上方遷移の果てに、本来は地中でしかなかった座標に新たな空洞が生じたに過ぎないのだ。人間はただ、意図せず崩壊の起爆装置を押しただけで、その後の経過は全く与り知らぬところにあった。

そして、本来の隧道の天井裏とでもいうべき空洞には、終わりが用意されていた。
ついに、足元を埋め尽くした瓦礫の山は、それと同じ色をした天井に接着し、空洞の系譜を閉ざした。最初に洞床に立ってから14分後、本隧道の完全な閉塞を確定させた瞬間だった。
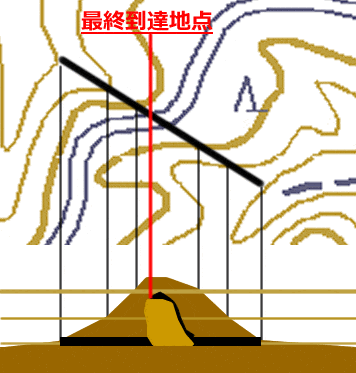
東坑口から進入した長さは、本来の隧道の長さ50m程度に加えて、崩壊により生じた高さ20mほどの竪穴の上で、終わった。この隧道の本来の全長は、実ははっきりとは分かっていない。ただ、地形的には100m程度と推定されている。したがって、最終地点は隧道の中央よりは西へ進んでいると思われる。計算上は、最終地点の瓦礫の床を20mほど掘り下げることができれば、西側の空洞に接続すると思われるが、もちろん実現は不可能であろう。

こんな場所に長居は無用である。登ってきた穴は、クレバスのように見通せない闇の底へと落ちており、もし引き返すのでなければ、とても立ち入る勇気は出なかったろう。だが今は、これだけが生存への道だった。
男鹿市で初めて見つけた廃隧道の完全閉塞を確認した私は、この大きな探索成果を世界に伝えるべく、仲間が待つ地上へ向けて動き出した。
ようやく、地上へ――

