このレポートは、「日本の廃道」2010年2月号および4月号に掲載した「特濃!廃道あるき vol.26」をリライトしたものです。
当記事は廃線探索をテーマにしており、不用意に真似をした場合、あなたの生命に危険が及ぶ可能性があります。当記事を参考にあなたが廃道へ赴き、いかなる損害を受けた場合も、作者(マイみちスト)およびみちこ編集室・道の駅連絡会は責を負いません。
所在地 山形県飯豊町〜小国町
探索日 平成21(2009)年5月10日
18:05
最初の大崩壊現場
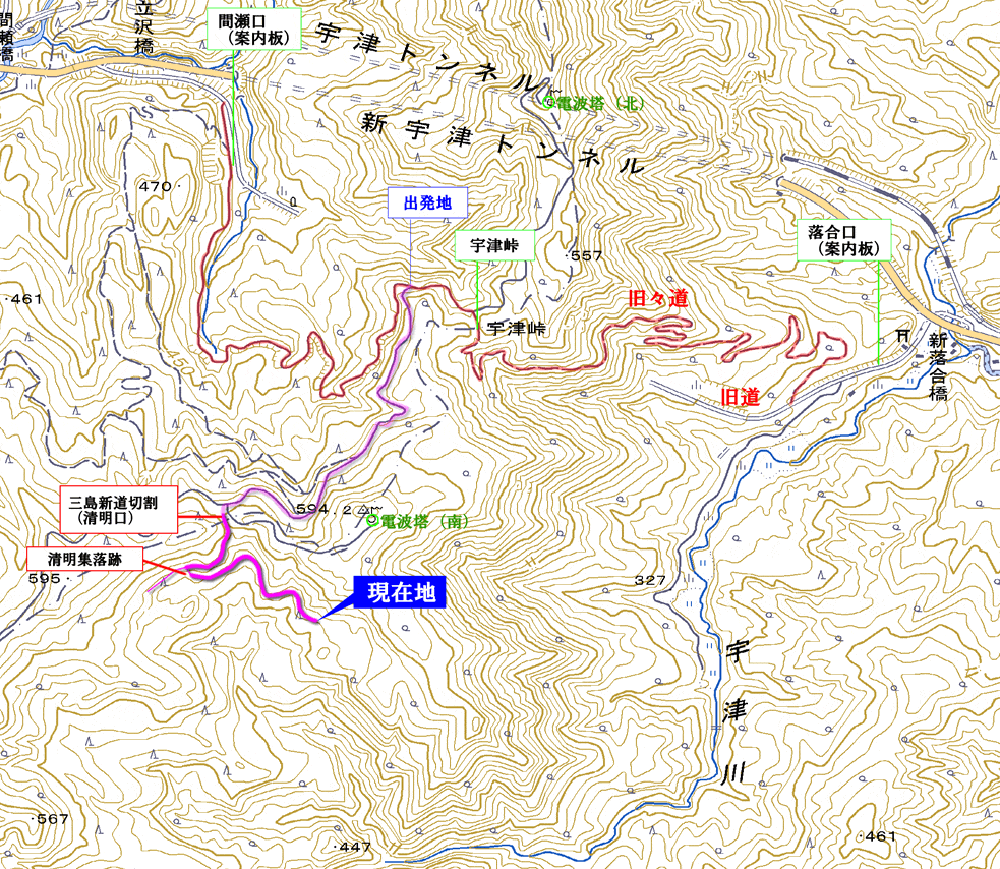

「三島新道堀割」から始まった今回の廃道探索。清明集落跡で一旦辿るべき道を見失い、探索の終了を宣言する一歩手前まで行ったものの、奇跡的に続きと思われる廃道を発見した後は、黙々と距離を稼ぎ、今は大きな崩落した砂地の斜面に向き合っている。
小さな谷を巻く道の左岸側が完全に消失している。そのため右岸末端から対岸に視線を滑らせても、見渡す限りに土の急斜面があるのみで、道の続きは見えない。普通なら、終点を疑ってもいい場面だ。

堀割からここまでの距離は約1km。標高は、掘り割りの550mに対して少しだけ下った510m付近だろう。地形図に描かれた地形を見る限り、現在地の周りは宇津川の左支源流谷の末端に近い比較的に緩傾斜な広葉樹林地帯である。だがその割に、眼前の崩落は険しく、かつ迂回困難な大きさを見せている。
はたして、三島通庸が率いた明治の土木設計士たちは、この地形的難局をいかに克服して先へ進んだのか。私はそれを見届けたかった。
それはそうと、現在時刻は午後6時を回っていた。こんな時間に探索をしている理由は、今回の廃道遭遇が突発的であったからに他ならないが、いくら日が長いシーズンといえども、私に許された明るい時間はもう僅かだ。既に日没を過ぎており、遠からず残光も消えて夜が全てを覆い隠すことになろう。ライトは持っているが、未知の廃道を夜に歩くことは、危険極まりない行為である。
冷静に振り返れば、このタイミングで、この場所で、前進という選択をすれば、ほぼ確実に闇の中に迷うことが分かっていたはずである。にもかかわらず引き返さなかった……否、今より10年分は未熟だった私が引き返せなかった理由は、目の前の廃道(しかも敬愛する三島通庸の未知の廃道だ)から引き下がりたくないという、シンプルな欲が強過ぎたからだ。
加えて、こことは世代が異なる宇津峠の廃道を、既に何度も越えているという自負もあった。それは慣れや驕りというものだった。どうせこの山はそんなに険しくないという侮りがあった。最悪途中で夜になっても、この山なら暗くても歩けるだろうという予想があった。
結果、三島通庸とヨッキれんの二人きりのセッションは、迫り来る夜闇に急かされつつも、より深い2人だけの時間へ深化していくのだった……。

100m近くも砂地の斜面をトラバースし続けて、ようやく平らな道形が復活した。だが安堵したのも束の間、前方には白っぽい空間が見えており、再度の砂地崩壊斜面の出現を予感させていた。

唐突なウド。山菜の中でも癖が少なく食べやすいので人気があるが、ウドが生えている場所はだいたいが土の崩壊斜面と相場が決まっている。特に晩春まで雪が残るような雪崩跡の斜面に群生しているのをよく見る。すなわち、廃道探索中に見るウドは、危険の匂いを多分に孕んでいる。
18:14
終わりの見えないトラバース
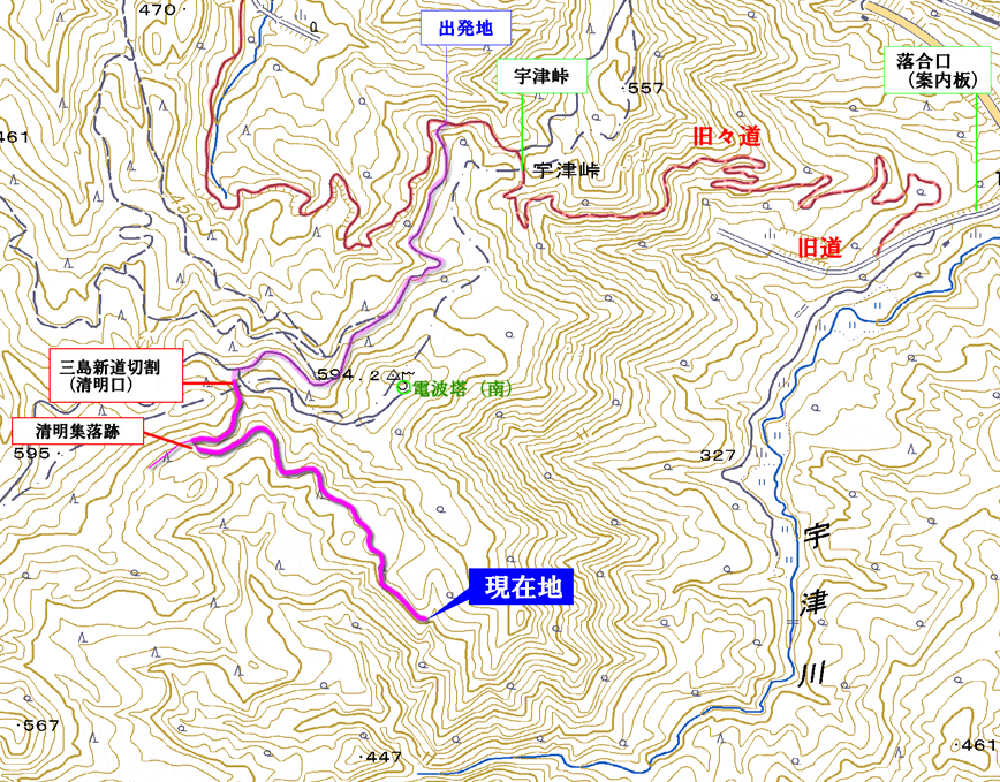

小さな土の崩壊斜面をいくつも踏み越えながら、黙々と早足で前進を続けた。時間がない。日没後の空は、灰梅から灰青へみるみる彩りを失っていく。特に撮影したくなるような対象が現われないこともあって、速歩していく。
にもかかわらず、道の終わりは窺い知れない。淡々と等高線に沿った南東方向へのトラバースが続いているが、周囲の地形は次第に険しくなっているのを感じる。ほとんど高度を下げていない。
地形図を見る限り、高度を下げて谷に近づくと傾斜がきつくなるので、下がらない方が安全ではあるだろうが、この道が麓を目指していくのであれば、下らないと終わらないぞ。どうなってんだ……。
18:25
宇津川の尾根カーブ
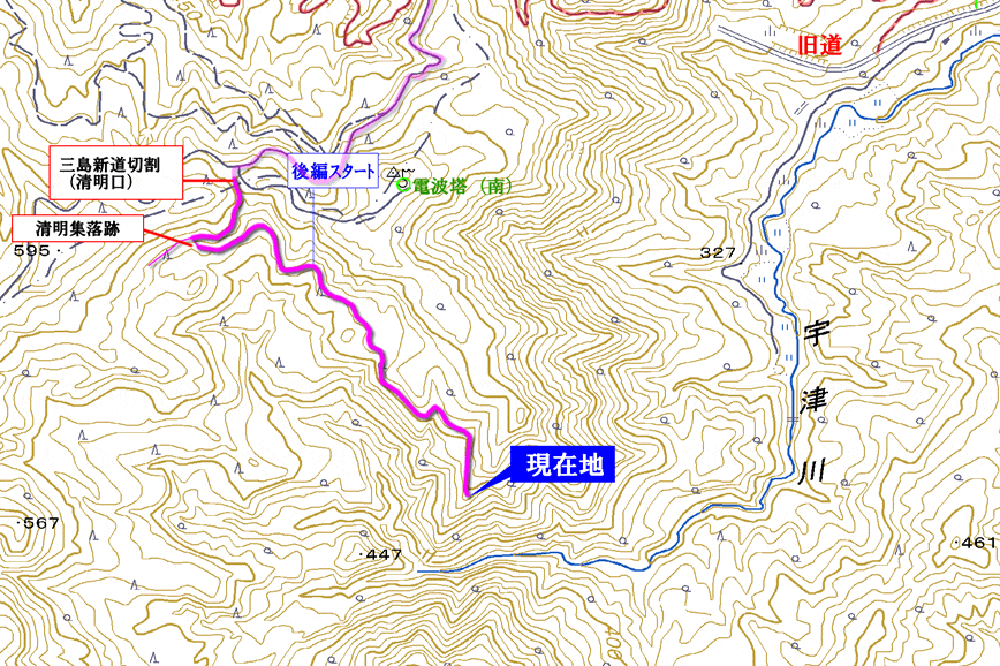

最初の大崩壊地を越えた20分後、長かったトラバースに変化があった。地形を見る限り、宇津川の高みに臨む尾根を回り込むところまで来たようだ。
いままでずっと深い緑の中で「底」を感じさせなかった宇津川の谷だが、ここで谷の対岸の山の位置がはっきり認識されたことで、足元に横たわる谷の規模や肉感が実感された。それで初めて、この道はこれから宇津川の谷を下っていって、最後には麓へ自力で到達するというそんな一連の筋道が想像できた気がした。
道がいま、峠から谷へと、バトンを渡した感じがした。

尾根の突端を巻くカーブを回り込むと、森の様子も変化した。周囲から高木が減り、やせ細った灌木ばかりになった。日中ならば陽当たりのよい道だったろうが、今は山谷を吹き抜ける冷たい風が、容赦なく頬にぶつかってきて、落ち着かない。なんだか、矢面に立たされたという心地がした。

ここが険しい山だと気づいたときには、もう……、
遅いんだよ…。

